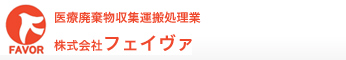「感染性廃棄物」って前からありましたっけ。
医療に従事する医師や看護師の方からよく頂く質問です。
経済成長と人口増加に伴って、地球規模での廃棄物増加と質の多様化が起こっています。
1950年代 環境衛生対策として「清掃法」という法律が制定されました。
その後、高度成長に伴う廃棄物の増加と公害への対策として1970年に「廃棄物処理法」が制定されます。
さらに廃棄物処理施設の整備や環境保全の為に度重なる法改正を行い、1990年代にはリサイクル法や有害物質対策、廃棄物の多様化に応じた処理法の制定や改定が行われました。

主な制定・改定を書き出してみると
1991年 廃棄物処理法改正
1991年 廃棄物処理法改正
1992年 産業廃棄物処理特定施設整備法制定
1992年 バーゼル法制定
1993年 環境基本法制定
1995年 容器包装リサイクル法制定
1998年 家電リサイクル法制定
1999年 ダイオキシン類対策特別措置法制定
2000年 循環型社会推進基本法制定(3Rの推進)
2000年 建設リサイクル法制定
2000年 食品リサイクル法制定
2001年 PCB特別措置法制定
2002年 自動車リサイクル法制定
2003年~2006年 2010年 産業廃棄物処理法改定
2013年 小型家電リサイクル法制定
とても多くて覚えられませんね。

不法投棄された医療廃棄物(1991年、日本)
高度成長期には廃棄物が起源となった事故事件が発生しました。
1955年 カドミウムを原因とした「イタイイタイ病」
1956年 メチル水銀を原因とした「水俣病」
これらの公害や、バブル期に問題となった大規模不法投棄事件や処理困難物問題、処分場不足問題などの責任を明確化し基本体制を整備するために多くの法律を制定し改定したのです。
感染性廃棄物は、感染症の起源となる可能性があるため、適切に処分する必要がある。として、防疫の観点から1992年に法的に規定されることとなりました。
その後、2000年・2003年・2004年に法改正され現在の処理方法が確立しました。
1992年の法改正により「感染性廃棄物」の処理方法が確立するまでは、注射針やオペ器具は一般的な「不燃物」として取り扱いされており、血液や組織片などは生ごみとして処理されていました。
当時、ごみの収集をしていた方に話を聞くと「ゴミ袋から注射針が飛び出していて、気付かずに持つとよく手や足に刺さっていた。」と懐かしく話されます。
今では考えられないことですが、当時は「注射針がゴミ袋に混ざっている。」はよくあることだったのです。

廃棄物処理法違反で摘発された医療ごみ(日本)
今では、法改正による厳罰化と各地域の保健所の方々の医療監視のおかげで、感染性廃棄物は分別して適正に処理をすることが当たりまえと根付いてきました。また、各処理施設の受け入れ基準が厳しくなり、注射針などの混入があった場合には受け入れ側の危険性を考慮し、当たり前に拒否されるようになったことも適正処理へのきっかけになったと思います。
話が長くなりましたが、「感染性廃棄物」は1992年に生まれた比較的新しい種類の廃棄物名称となります。
「感染性廃棄物」は、特別に管理する必要がある産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)として法規定されています。
排出される皆様もそうですが、受け取り側の安全もご考慮頂きまして今後の分別、適正量排出へのご協力をよろしくお願い申し上げます。